犬と猫の混合ワクチン|種類と選び方の完全ガイド【獣医師が解説】
愛犬や愛猫を感染症から守るために欠かせない「混合ワクチン接種」ですが、一方で「室内飼いだから必要ないのでは?」「どの種類を選べばいいの?」と迷われる飼い主さまも多いのではないでしょうか。
今回は、生活環境や年齢に合わせたワクチンの考え方を、獣医師の視点から解説します。

■目次
1.混合ワクチンとは?目的と基本の仕組み
2.犬と猫のワクチンの種類と対象疾患
3.接種のタイミングと注意点
4.シニア期のワクチン接種は必要?
5.まとめ
混合ワクチンとは?目的と基本の仕組み
ワクチンは、犬や猫の体に「免疫(感染症に対する防御力)」をつくることで、病気の発症や重症化を防ぐためのものです。一度感染してしまうと命に関わることもある感染症に備えるための「予防医療」のひとつといえます。
なかでも「混合ワクチン」は、複数の感染症に対して一度の接種で免疫をつけられるように、いくつかの病原体を組み合わせて作られたものです。生活の中で感染リスクがある複数の病気をまとめて防ぐことができます。
ただし「どのワクチンが良い・悪い」というものではありません。外に出る頻度、他の動物との接触機会、同居動物の有無など、生活環境によって適した内容は変わります。また、人の衣服や靴を介してウイルスが持ち込まれることがあるため、完全に室内で暮らす犬や猫でもまったくの“ゼロリスク”とは言えません。
当院では、飼い主さまと一緒にお話をしながら、その子の性格や暮らし方に合ったワクチンプランを考えています。
犬と猫のワクチンの種類と対象疾患
混合ワクチンは、犬では5種・7種・8種、猫では3種・5種などのタイプがあります。
数字が大きいほど予防できる病気の範囲が広がりますが、どれが正解というわけではありません。その子の生活スタイルや体質に合わせて選ぶことが大切です。
<犬の混合ワクチン>
| 対象疾患 | 感染経路・特徴 | 5種 | 7種 | 8種 |
| 犬ジステンパー | 飛沫や接触で感染。発熱・咳・神経症状を起こす重い感染症。 | ○ | ○ | ○ |
| 犬パルボウイルス感染症 | 排泄物などから感染。激しい下痢・嘔吐を起こし、子犬では命に関わることも。 | ○ | ○ | ○ |
| 犬アデノウイルス(伝染性肝炎)※ | 感染犬の尿や唾液から感染。肝臓障害や発熱を伴う。 | ○ | ○ | ○ |
| 犬パラインフルエンザ | 咳や鼻水を起こす「犬風邪」。接触や空気中の飛沫で広がる。 | ○ | ○ | ○ |
| 犬コロナウイルス感染症 | 主に消化器に症状。軽度だが他の感染と重なると悪化することも。 | ○ | ○ | ○ |
| レプトスピラ症(イクテロヘモラジー型など) | げっ歯類の尿に汚染された水や土から感染。肝臓や腎臓に障害を起こすことがあり、人にも感染する。 | - | ○ | ○ |
| レプトスピラ症(カニコーラ型など) | 同様に水や土を介して感染し、人にも感染する。腎臓に慢性的な炎症を起こすことがある。 | - | - | ○ |
※犬アデノウイルスには1型(犬伝染性肝炎)と2型(犬伝染性喉頭気管炎)があり、現在のワクチンは2型を使用することで両方の感染症を予防できます。
5種ワクチンは「主に犬同士の感染症」を、7〜8種ワクチンは「人にも感染する病気を含めた広い予防」をカバーします。屋外活動が多い子や多頭飼育の環境では7種以上が推奨されることもあります。
<猫の混合ワクチン >
| 対象疾患 | 感染経路・特徴 | 3種 | 5種 |
| 猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペスウイルス) | くしゃみ・鼻水・目やにを起こす猫風邪。飛沫・接触で感染。 | ○ | ○ |
| 猫カリシウイルス感染症 | 猫風邪の一種。口内炎や発熱を起こし、唾液・くしゃみで感染。 | ○ | ○ |
| 猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス) | 強い下痢・嘔吐を起こす重い感染症。排泄物などから感染。 | ○ | ○ |
| 猫白血病ウイルス感染症(FeLV) | 猫同士のグルーミングやけんかで感染。免疫低下・腫瘍・貧血を起こす。 | - | ○ |
| 猫クラミジア感染症 | 結膜炎や目やにを起こす。接触感染が多く、集団飼育環境で広がりやすい。 | - | ○ |
「完全室内飼いだから大丈夫」と思われがちですが、ウイルスは人の衣類や靴に付着して持ち込まれることもあります。リスクを「ゼロにする」のではなく「減らすための備え」がワクチンです。
ワクチン選びは「何を守りたいか」を考えることから始まります。当院では、年齢・生活環境・体調を踏まえ、“その子に合った最適な選択”を一緒に考えることを大切にしています。
接種のタイミングと注意点
混合ワクチンは、一度接種して終わりではありません。感染症に対する免疫は時間の経過とともに弱まるため、子犬・子猫の時期から段階的に免疫をつくり、定期的に維持していくことが大切です。
<初回接種から追加接種までの流れ>
子犬・子猫は、生後6〜8週頃(母犬・母猫から受け継いだ免疫が切れる時期)から接種を始めます。
その後、3〜4週間おきに2〜3回追加接種を行い、しっかりとした免疫を定着させていきます。この時期の接種は「感染症に対する防御力を育てる期間」です。1回で終えると十分な免疫がつかないことがあるため、複数回の接種を完了することが重要です。
成犬・成猫になってからも、免疫は時間とともに少しずつ低下します。そのため、年に1回程度の追加接種(ブースター)で免疫を維持することが推奨されています。このブースターには「これまでに作られた免疫を思い出させ、再び強化する」役割があります。
<接種前後のチェックポイント>
ワクチンの効果をしっかり発揮させるためには、接種のタイミングだけでなく、体調の見極めや接種後のケアも大切です。
▼接種前に確認したいこと
体調が万全ではないときに接種すると、免疫のつき方が不十分になることがあります。少しでも気になることがあれば、無理せず日を改めましょう。
☑ 食欲・元気・排便の状態に異常がないか
☑ 発熱や下痢など体調不良がないか
▼接種後に気をつけたいこと
一時的に発熱や注射部位の腫れが見られることがありますが、多くは自然におさまります。
ただし、次のような様子がみられる場合は、すぐに動物病院へご相談ください。
☑ ぐったりしている
☑ 呼吸が荒い
☑ 嘔吐が続く
<当日の過ごし方>
接種後は、体が免疫をつくる準備をしている大切な時間です。いつもより少し静かに、ゆっくりと過ごさせてあげましょう。
・散歩やシャンプーは控え、静かな環境で安静に過ごす
・水分をしっかりとらせる
・多頭飼いの場合は、一時的に他の子と分けて様子を見る
事前のコンディションと接種後の過ごし方に気をつけてあげることで、より安心して受けていただくことができます。
シニア期のワクチン接種は必要?
年齢を重ねた愛犬・愛猫に「もうワクチンは必要ないのでは?」と感じる飼い主さまもいらっしゃるかもしれません。
しかし、加齢に伴って免疫力は少しずつ低下していくため、年齢だけで「もういいか」と判断してしまうのは注意が必要です。体の防御力が落ちると、若いころには軽く済んでいた感染症でも重症化してしまうことがあります。
一方で、持病がある場合や体調の波が大きい子では、ワクチンの刺激が体に負担となることもあります。そのため「打つかどうか」だけでなく「いつ・どんな形で受けるのが安心か」を一緒に考えることが大切です。
<当院の考え方>
Ken doc.では、シニア犬・シニア猫のワクチン接種を「年齢」で一律に判断することはありません。
その子の
・健康状態
・生活環境(室内か屋外か、他の動物との接触など)
・既往歴や持病
といった情報をふまえ、獣医師が一頭ずつ丁寧にリスクとメリットを見極めながら判断します。
たとえば、体調が安定しているシニア犬には、負担の少ないスケジュールでの接種を検討します。一方で、持病がある場合には、血液検査などで全身の状態を確認しながら、接種を見送ることもあります。
「本当にうちの子にも必要?」という迷いを持たれるのは、自然なことです。当院では、不安を抱えたまま決めるのではなく、獣医師と相談しながら最適な方法を一緒に考えることを大切にしています。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
混合ワクチンは、犬や猫を感染症から守るための大切な“防具”です。しかし「どの種類がいいのか」「シニア期も続けるべきか」は、それぞれの生活環境や体調によって異なります。大切なのは、年齢や一般的な基準だけで決めるのではなく、その子の今の状態に合わせて考えることです。
当院は愛知県みよし市で、地域に根ざした動物病院として飼い主さまと一緒に悩み、話し合いながら、無理のない最適なワクチンプランをご提案しています。「うちの子にはどのワクチンが合うのかな?」そんな小さな疑問からでもかまいません。どうぞお気軽にご相談ください。
◼こちらの関連記事もご覧ください
愛知県みよし市にある犬と猫の病院「Ken doc.」
お問い合わせはこちら
投稿者プロフィール

- 愛知県の動物病院
- 愛知県みよし市にあるKen Doc.は、犬や猫のためだけの動物病院です。入院室、手術室、そしてICUなど、充実した設備を備えており、大切なペットの健康をしっかりとサポートします。また、獣医師や愛玩動物看護師の求人情報も随時募集しています。Ken Doc.で、あなたのペットの健康を守るためのパートナーとなります。
最新の投稿
 ブログ2026年2月20日寒い時期に増える犬の急性胃腸炎|様子見でいい?受診すべき?
ブログ2026年2月20日寒い時期に増える犬の急性胃腸炎|様子見でいい?受診すべき? ブログ2026年2月20日「元気がない」は寒さのせいかも?シニア犬の冬の低体温症と対処法
ブログ2026年2月20日「元気がない」は寒さのせいかも?シニア犬の冬の低体温症と対処法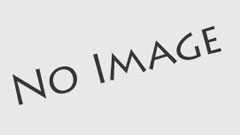 緊急のお知らせ2026年2月16日年末年始の診療時間変更について
緊急のお知らせ2026年2月16日年末年始の診療時間変更について 採用関連2026年2月3日test採用02
採用関連2026年2月3日test採用02
タグ一覧
- RECOVER CPR
- SFTS
- おしっこの回数が増える
- お知らせ
- かゆい
- しこり
- しつけ
- ふけ
- ぶどう膜炎
- アトピー
- アニクリ24
- アレルギー
- オンライン予約について
- ケア
- ケンカ
- ゴールデン・レトリーバー
- シニア犬に多い病気
- シー・ズー
- ズーノーシス
- チワワ
- トイ・プードル
- フレンチブルドッグ
- フード
- ヘビ咬傷
- ポメラニアン
- マダニ
- マラセチア
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
- ヨークシャー・テリア
- ワクチン
- 下痢
- 不整脈
- 予防
- 会陰ヘルニア
- 便が出ない
- 健康チェック
- 健康診断
- 僧帽弁閉鎖不全症
- 内視鏡下バルーンダイレーション
- 副腎皮質機能低下症
- 口を痛がる
- 口唇粘膜炎
- 口臭が強くなる
- 咳
- 嘔吐
- 変形性関節症
- 多飲多尿
- 夜間緊急診療
- 子犬
- 子猫
- 徘徊
- 心筋症
- 心肺蘇生
- 応急処置
- 性格の変化
- 怪我
- 愛玩動物看護師
- 感染症予防
- 慢性腎臓病
- 救急
- 散歩を嫌がる
- 柴犬
- 栄養管理
- 歯が抜ける
- 歯のケア
- 歯周病
- 毛玉
- 気管支炎
- 気管虚脱
- 水をよく飲む
- 治らない
- 爪とぎ
- 犬
- 猫
- 生活習慣
- 症状
- 白内障
- 皮膚検査
- 皮膚炎
- 目が見えない
- 目をこする
- 眼球摘出術
- 睡眠
- 研修プログラム
- 社会化
- 糖尿病
- 緑内障
- 脱毛
- 脾臓
- 腫瘍
- 診療科
- 認知症
- 誤飲誤食
- 足を引きずる
- 食中毒
- 食欲が落ちる
- 食欲旺盛なのに体重が減る
- 食道狭窄
- 黒目が白っぽくにごる










